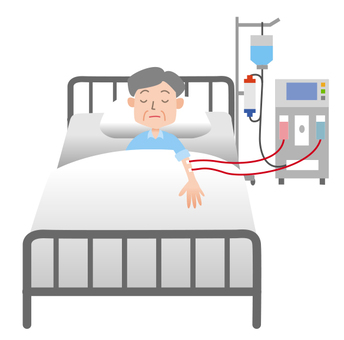札幌腎臓病患者友の会(札幌腎友会)は、札幌市、石狩市、当別町、恵庭市、北広島市、千歳市、新篠津村の腎臓病患者の患者会です。札幌市を中心とした腎臓病に関する知識の普及、腎臓病患者の医療体制の充実と福祉の向上を図るために活動しています。
※新着情報
2024/4/14
運営会議を行いました。
2024/03/22
大塚製薬の紅麴被害の疑いについてを追加しました。
2024/03/07
トップページの写真を変更しました。
2024/02/22
ホームページはリニューアルしました。
※お詫び
「生きる仲間138号」に掲載された「人工腎臓の軌跡」の内容が間違っていると指摘を受けました。
現在も「猪野毛建男医師」はご高齢ですが、ご存命だという事が当会で確認で出来ました。お詫びをするとともに、今後このようなことがないように気を付けて参ります。
ご迷惑をおかけしました方々には、謹んでお詫び申し上げます。
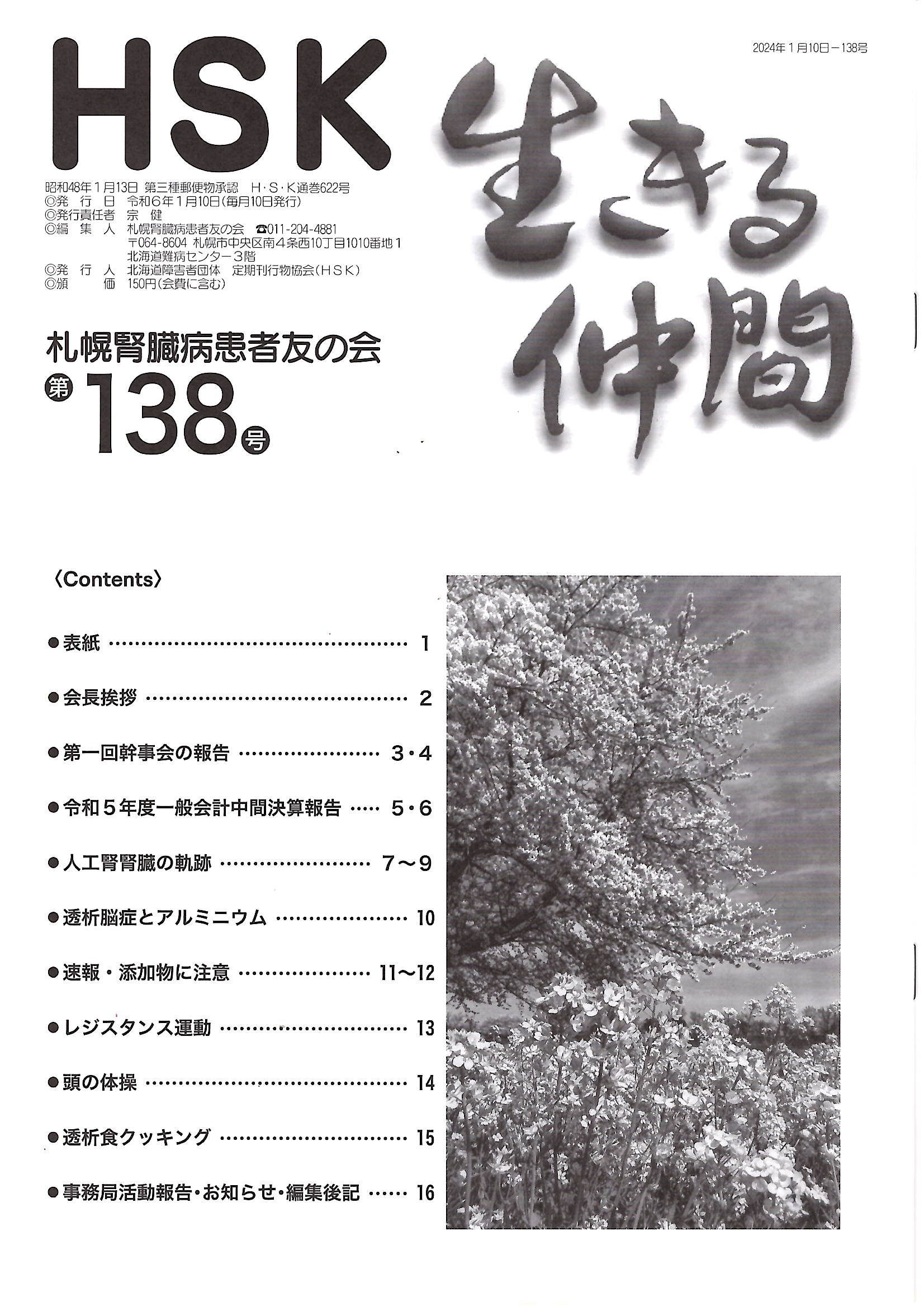
※生きる仲間138号
○令和5年度会計中間決算報告
○新薬情報、
○添加物に注意
○透析脳症とアルミニウム
○レジスタンス運動、
○透析食クッキングなど
●機関紙「生きる仲間」は年2回の発行です。会員さんには配布済みなのでご意見などありましたらお寄せ下さい。
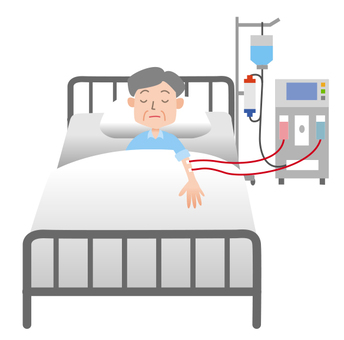
※人工透析はどうして必要か?
人工透析は、腎臓の機能が低下し、体内に溜まった老廃物や余分な水分を血液から取り除く治療法です。腎臓は血液中の老廃物や余分な水分を尿として排出しています。
しかし、腎臓が正常な状態の1割以下になると血液のろ過が十分に行えなくなり、尿の異常のほか、浮腫老廃物や余分な水分が体内に溜まり、体調不良や命にかかわる症状が現れます。
透析療法は腎臓の機能を回復させるわけではなく、機能を人工的に補助するもので、赤血球を作る「造血ホルモン」や「内服薬」など、透析で代替できない機能については補う必要があります。
人工透析は腎臓の代わりに血液を浄化する方法です。
1週間透析をおこなわないと死んでしまう恐れがあるので、必ず透析を受けるようにしましょう。
参考文献 : Medical Note、ウィキペディア、透析の歴史、透析患者の合併症、Resou(リソウ)、透析百貨、機関紙「生きる仲間」など。
本格運用開始日 : 令和5年4月1日